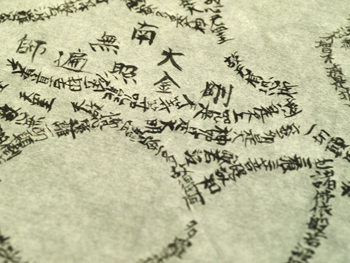氷嚢釣(ひょうのうつり)

2015年の現代の日本では、代替テクノロジーの進歩ですっかりと出番がなくなった氷嚢釣、この写真は50数年前の1960年代の木製組立式の氷嚢釣のヘッド部分です。 その昔、風邪などで熱が出たとき頭を冷やすときに使われた道具で、土台部分を布団頭部の下に差し込んで固定し、突き出した棒のところに氷を入れた袋(氷嚢)を額に当たるように吊り下げ、頭の上から氷嚢、下から氷枕、という具合です。 現代でも氷嚢スタンドなどの名称で金属製のものが流通しているようですが、金属やプラスチックが隆盛する前の道具類はこうした木製で、この氷嚢釣は氷袋を引っかける棒の先端に金具がついている以外、他はすべて木で、壊れて破棄するとしても、分別面で誠にエコ仕様です。 シンプルでマニアックな機能的な造形は、豊かで美しく、とてもおもしろい。 *組み立てるとこんな感じです。 *手前右に見えるものは、氷を細かく砕くためのツール。 *手前左の部品は、 高さ調整用の固定ねじ。